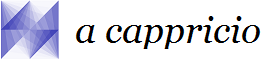編者による前書き(続き)
さて、光栄なことに、私はRKの最期の作品を出版に向けて取りまとめるという仕事を任せていただきました。今やこの「Principles of Orchestration」は書籍として出版されているわけですから、この本の本質的な特徴や、私が編集者として本書にどのように手を加えたかということについて少しご説明いたします。
まず本書の特徴についてですが、私から述べることはほとんどありません。目次だけでも他の教科書とは違うということが読み取れるでしょう。これは単に作例が第二巻に分かれているというような見た目の問題ではなく、各章の単元がより系統的に学習できるように並んでいるということです。つまり、例えばGevaertの教科書に見られるような単にオーケストラを楽器ごとに分類して順番に学習していくのとは対照的で、音楽全体の中における個々の役割(メロディ、和声など)に着目して学習を進めるスタイルになっています。メロディと和声のオーケストレーション(第二章及び第三章)は特に注意深く書かれており、第四章ではオーケストレーションを実践する上で実際に出くわす様々な問題についてやはり丁寧に扱っています。第五章と第六章はオペラの作曲を見越して書かれたものです。ただし第六章は歌の扱いに関する補足という形をとっており、他の章との直接の関係は薄くなっています。
RKはこの教科書のタイトルを何度も考え直しており、結局最終決定をしないままに旅立ってしまいました。いくつかの候補の中から私が選んだ「Principles of Orchestration」というタイトルは、本書の内容に最もそぐうものであると思います。そう、本書はまさにオーケストレーションのPrinciple (露основы:基礎、土台) を説明した本なのです。もしかすると、本書によってRKという偉大なオーケストレーターの「秘技」が明らかになったと考える人もいるかもしれません。しかし、彼自身による前書きの言葉を借りれば、「オーケストレーションとは創造的な作業であり、これは指導できる類のものではない」でしょう。
それでも、あらゆる芸術において創造性というものは技術と結びついているものですから、本書は管弦楽法を学ぶ者に非常に役立つことでしょう。オーケストレーションの公理としてRKが何度も繰り返していたのは、「良いオーケストレーションとは即ち卓越した声部の取り扱いにある」という言葉です。これ以外の事柄として、それぞれの音色や混合音色をどう使うかということも本書から学ぶことができますが、指導できるのはここまでです。これらの点を鑑みれば、本書はRKの伝えたかった事のほぼ全てを読者に伝えるものになっています。RKを襲った志半ばの死は、いくつかの疑問について尋ねる機会を奪ってしまいました。例えば完全にポリフォニックな場合のオーケストレーションやメロディと和声を併せ持つようなフレーズのオーケストレーションなどです。しかし、これらの疑問については、少なくとも部分的には、第二章と第三章に記された原則が答えを与えてくれます。ですので、私は本書の初版に色々書き足して情報を詰め込もうとは思いません。もし本当に必要なら、それは第二版以降で取り組みます。私はなによりもまずRKが1905年の夏に残したメモを整理し、全六章の教科書としてまとめあげなければなりませんでした。第一章はRK自身の手によってまとめられたもので、書式等の些細な修正を除けばそのままの形で出版しています。続く五章分については、可能な限り元の原稿を変えないようにしましたが、それでも一部順番を入れ替えたほか、一ヶ所か二ヶ所程度、不可欠と思われる説明を追記することになりました。なお、1891-1893年に書かれたメモはそのまま使うには最終版とあまりにもかけ離れているものでしたが、内容としては最終稿にかなり通じたものでした。
作例の紹介はさらに重要です。1891年のメモによれば、もともとの構想ではグリンカとチャイコフスキーの音楽から作例を紹介するつもりだったようです。また、後になってボロディンとグラズノフの音楽も加えるという構想が追記されています。しかし、次第に作例をRK自身の曲に限定するというアイディアが生まれてきました。この理由について、ある程度は1905年に書かれた未完の前書きにて説明されていますが、ここではそれ以外の理由を紹介しましょう。もしRKが作例をこれら四人の音楽から引用した場合、RKはそのそれぞれが持つ独自の(しかも往々にしてかなり奇抜な)作風についていくらかの説明を加えなければならなくなります。これはそう簡単な仕事ではありません。そのうえ、西ヨーロッパの作曲家(例えばワーグナー)を省いた理由を提示しなければならないでしょう。RKは彼らのオーケストレーションも常に称賛していたのですから。しかし、彼自身の作品はそれだけであらゆるオーケストレーションの手法を紹介できる程豊富であり、しかもこれらのテクニックは筋の通った一つの考え方によって説明できるものです。RKはこのことを十分自覚していました。ここでは作例を自作に限ったことの良し悪しを議論することは避けますが、RKの「学校」は本書を持って市井に晒されました。後は読者の皆様それぞれが判断されることでしょう。RKがグリンカを尊敬して倣い学んできたように、RKの手法はロシアの作曲家や若いフランスの作曲家に受け継がれ、一層華麗で色彩感に富んだオーケストレーションへと発展を続けています。
編集にあたり、私はRKの意向に則って次の事柄を意識しました。まず、作例はできる限りシンプルにすること。そうでない限り、読み手はそこで問題にしている事柄以外のことにまで気を取られてしまいます。次に、一つの作例が本書の様々な章で参照できること。そして最後に、作例の大部分をRK自身による引用とすることです。第二巻に収録した作例の内訳は、RK自身が引用したものが214例、私が追加したものが98例となっています。これら作例は、可能な限りRKのオペラから選び出しました。というのは、オペラの総譜というのは交響曲に比べて入手が困難だからです(RKの交響曲については、最近Belaieffがポケットスコアを出版しました)。
第二巻の最後に、オーケストラ全体を使った和音の書き方を示す表を3つ追加しました。また、私が本文で追記したもの、あるいは私が追加した作例については、アスタリスク(*)を付しています。また、いろいろな作曲家による作品をいきなり研究し始めるよりも、第二巻収録の作例をよく勉強するほうが高い学習効果が得られると思います。たいていの場合は、そのフルスコアを参照しながら勉強するのが良いでしょう。
ここで、RKの作品にも誤りがあるということを指摘しておかなければなりません。誤りの指摘は、彼が最後に書いた前書きにあるように、彼自身が望んでいたことです。RKは、教育という意味においてこのような誤りについて考えることの重要性についてよく漏らしていましたが、結局具体的な形を残せないまま亡くなってしまいました。誤りとしてここに挙げる2例は私が選んだものではなく、RK自身が指摘していたものです。
- The Legend of Tsar Saltan, 練習番号220, 7小節目: 金管によるテーマは、トロンボーンが休んでしまっているためにあまり目立たない(修正は容易)
- The Golden Cockerel, 練習番号 233, 10-14小節目: 金管を指定通りの音量で演奏してしまうと、ヴィオラとチェロによる対旋律(木管で重複)がほとんど聴こえなくなる
第二巻に収録した作例No. 75 (Sadko)にも誤りがあります。これについては、本文50ページの注で解説しています。というわけで、誤りの指摘はこれくらいにしておきましょう。
最後に、私を信頼して編集作業を任せてくださったリムスキー=コルサコフ夫人に深い感謝を申し上げます。そのおかげをもちまして、尊敬してやまない師であるニコライ・アンドレイェヴィチ・リムスキー=コルサコフが最期に遺したものに対する私の義務を果たすことができました。
1912年12月、St. Petersburghにて
Maximilian Steinberg