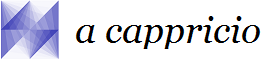編者による前書き
ニコライ・アンドレイェヴィチ・リムスキー=コルサコフ(Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov; 以下RK)は、その生涯の長期に渡ってオーケストレーションの手法を書き残してきました。私たちの手元にも、1873-1874年にかけて記された200ページもの手書きのノートがあります。そのノートは音響に関する一般的な説明から始まり、続いて管楽器の分類についての説明、そしてそれら管楽器(オーボエ、クラリネット、ホルン、種々のフルート)の扱い方まで記されています。
注:このノートはAlexander Glazounovから寄贈されたものです。
彼は、自伝「わが音楽の生涯(Memoirs of my musical life)」にて次のような言葉を残しています(第一版p120より)。
注:「わが音楽の生涯」は服部竜太郎氏による翻訳が出版されているが、この訳は平沢奏汰による。
私は過去にも、オーケストレーションの完全な解説書を作り上げるために私の全精力を捧げようと考えていた時期があった。この目標に向け、まず私はそれぞれの楽器の扱い方を書き留めたメモをいくつか作ったのだ。この時私が成し遂げたかったのは、オーケストレーションにかかわるあらゆる事柄を網羅的に説明するということである。この解説書、いやもっと正確に言えばそのためのメモやスケッチを書いていたのは1873-1874年にかけてのことで、この間私はほとんどそれに没頭していた。解説書の序論はTyndallやHelmholtzによる物理学の教科書を読んでから書き始めたもので、そこでは楽器製作に関係する音響学の理論について解説することに努めた。当初、この解説書は、楽器をそれぞれ分類して表にまとめた詳細な楽器一覧を出発点とする予定でいた。そこで現代の楽器に用いられる様々な発音機構も同時に紹介するのである。ちなみにこの時はまだ、続く章で楽器の組み合わせ方について説明するというアイディアはなかった。ともあれ、私はすぐにこれは思い上がった解説であると気が付いた。特に木管楽器には無数の機構が存在し、製作者によって好むやり方が変わってくる。楽器メーカーはある種のキーを付け足すことで、これまでできなかったトリルを可能にしたり、難しいパッセージを他の楽器よりも簡単に演奏できるようにしたりという工夫を重ねてきた。
リムスキー=コルサコフ『 わが音楽の生涯 』
このような楽器の複雑化は終わりを見せない。金管の場合でも、3つから5つにもわたるバルブを持つ楽器を見たことがある。しかも、そのメカニズムはメーカーによって異なるのだ。どう考えても、私にはこれほど多岐にわたる楽器機構の全てを紹介することなどできまい。それに、例え可能だったとしても、このような機構の全てを説明することが読者にどう役立つのだろうか。各楽器の機構やその利点と欠点を詳細に説明して見せたところで、このような大量の解説は読者を混乱させ、学習意欲を奪うだけだろう。そんな解説を読んだ読者はどう考えるだろうか。当然、「自分がこの本から学びたかったのはどの楽器を使えばよいか、あるいはどのようなものが演奏可能でどのようなものが演奏不可能なのかということだったのに」と解説に失望することだろう。そうして、その分厚い本を読むのをやめてしまうだろう。これに気付いたところから、私の教科書に対する興味は徐々に薄れていき、ついにはこれを諦めたのだった。
1891年、RKは既に「Snegourotchka」「Mlada」「Scheherazade」などの作曲で名を挙げ、オーケストレーションの第一人者として知られていました。教育に携わってからも20年を数えており、教科書の作成へと再び乗り出していました。1891-1893年にかけて改めてスケッチノートを作成していたようで、この間、Mladaの初演後はしばらく作曲に時間を費やすことを諦めていました。ここで作成したメモは時々「わが音楽の生涯」でも引用されていますが、全三章からなる原稿にまとまりました。この原稿は1891年に書かれた未出版の前書き*や、明快で思慮に富んだ内容のパラグラフを含んでおり、本書で改めて日の目を見るものです。
注: この前書きはすでに「Notes and Articles on Music」(St. Petersburgh, 1911)にて出版されている。
RK自身が「わが生涯」(p. 297)で述べている通り、この教科書の執筆は必ずしも順調とは言えず、また彼は多くの面倒ごとに巻き込まれていたのでした。結局彼は自身の書いた下書きの質に納得できずにその大部分を破棄し、またしても教科書の執筆から距離を置いてしまいます。
彼の人生に転機が訪れたのは、1894年。彼はこの年にオペラ「Christmas Eve」を作曲します。これが、彼にとって最も栄光に満ちた輝かしい時代の始まりとなりました。彼は持てる時間の全てを作曲に注ぎ、ある時点で手掛けているオペラが終わり次第すぐに次作に取り掛かれるほどの計画を練り続けます。このように音楽家として作曲に熱中した時代は1905年ごろまで続きましたが、またしても外部からの色々の影響によって作曲を中断することになりました。そうしてまた、彼の興味がオーケストレーションの教科書を作ることに戻っていったのです。ただし、教科書の内容に関する構想は、1891年の時点で思い描いていたものから全くと言っていいほど変わりました。これは現存する当時の下書きからも明らかです。最終的に、個々の楽器について技術的な側面から説明するのを諦め、その音質や組み合わせ方により重きを置くようになります。
彼の遺したノートを見る限り、彼は細部のかなり異なるいろいろなバージョンを作っていたようです。最終的に構想を固めたのは1905年のことで、ついに本書の土台となる全六章からなる解説書の作成に着手しました。しかし、またしても作業が中断してしまい、この構想は一旦脇に置かれることになったのです。「わが生涯」では、RKはこれを興味の喪失と退屈感によるものとし、次のように書いています。
教科書の執筆は中断したままだ。なによりも、教科書の全体像に満足がいかなかった。それに、この本を書くためには「Legend of Kitesh」の完成を待たねばならなかった。なにしろ、この曲からも作例を紹介したかったのだから。
リムスキー=コルサコフ『 わが音楽の生涯 』 p. 360
1906年、秋。この頃、RKは再び精力的に作曲に取り組んでいました。オペラ「The Golden Cockerel」が大成功をおさめ、その冬はおろか1907年の夏まで多忙な日々が続いたのです。そしてその年の秋ごろ、ようやく落ち着いたRKは改めて教科書の作成に乗り出します。進捗は思わしくありませんでした。思い描いた構想が妥当かどうか自信を持ち切れず、友人や生徒たちが完成を待ち望むにもかかわらず、本の後半を書ききることができなかったのです。そして同じ1907年の終わりにかけて、彼は慢性的な不調を訴えるようになります。これが、彼の熱意に火をつけました。彼は持てる時間のほとんどを、昔のメモを読んだり作例を分類したりするのに費やしました。1908年5月20日頃、彼はリュベンスクにある別荘に向け出発します。そして3度目となる苛烈な肺炎発作から回復して間もなく、ついに解説書の第一章を最終稿、つまり現在遺されている版へとまとめる作業に取り掛かったのです。第一章が仕上がったのは6月20日、午後4時頃。そしてその明朝未明。4度目の発作によって、彼はその生涯に幕を降ろしたのです。